冷蔵庫に残った昨日のお刺身…
「これって、まだ食べても大丈夫?」、そんな風に迷ったこと、ありますよね?
お刺身って、生ものだけに扱いがデリケート。
消費期限が「昨日」だったりすると、もったいないけど処分すべきかどうか悩ましいところです。
実際のところ、翌日に食べてもいいケースと、やめておいた方がいいケースがあります。
この記事では、
など、気になる点をやさしく・わかりやすく解説していきます。
さらに、「お寿司」の消費期限に関する関連記事(▶︎お寿司は消費期限が切れても翌日食べられる?安全な見極め方と保存・アレンジ方法!)もご紹介していますので、お刺身とあわせてぜひ参考にしてみてください。
では、さっそく「翌日でも食べられるのか?」について、具体的に見ていきましょう!
冷蔵庫に残ったお刺身、翌日に食べても大丈夫?

冷蔵庫に入れておいた昨日のお刺身の残り、消費期限は昨日だけど、まだ食べられるかな?
そんなふうに思ったこと、きっと一度はあるんじゃないでしょうか。
でも、生ものはやっぱり不安。
ここでは、そもそも消費期限って何なのか、そして翌日に食べてもいいケースとダメなケースの判断ポイントをわかりやすく紹介していきます!
そもそも「消費期限」とは何か?
まずはここから。
お刺身のパックに「消費期限:○月○日」と書かれているのを見て、「あれ?賞味期限とは違うの?」と思ったこと、ありませんか?
実はこの2つ、意味がはっきりと違います。
・消費期限:安全に食べられる期限(過ぎたら食べない方がいい)
お刺身は、生の魚を扱うため食品衛生上とてもデリケート。そのため、販売されているお刺身にはほとんど「消費期限」が設定されています。
つまり、「消費期限切れ=食べるとお腹を壊すリスクがある」ラインだと理解しておくのが基本です。
消費期限が切れたお刺身は食べられるのか?
それじゃ、「消費期限が切れたお刺身は絶対にダメなの?」、そんな疑問にここからお答えします。
実は、保存状況や見た目・においのチェック次第では、まだ食べられることもあるんです。
安全に食べられるケース
次のような条件が揃っている場合、自己責任のもとで食べられる可能性はあります。
・消費期限から1日以内
・におい・見た目に異常がない
・ドリップ(汁)がほとんど出ていない
・加熱調理や漬けなど、アレンジして食べる
特に、残ったお刺身を翌日に食べる場合はそのまま食べるよりも、火を通す・漬けにする・マリネにするなど、殺菌や保存の意味合いを含んだアレンジが安心です(この点については後のセクションで詳しく紹介しますね)。
食べない方がいいケース
逆に、次のような状態であれば、迷わず処分をおすすめします。
・においが「ツン」とする、生臭さが強い
・ぬめりがある
・ドリップが多く出ていて、変色している
・冷蔵庫の外に放置していた時間がある
特に夏場などは、冷蔵庫内でも菌が増殖しやすい環境になることがあるので要注意。体調を崩すリスクと天秤にかけたとき、無理して食べるメリットはありません。
傷んだお刺身の見分け方!こんな状態はNG!

冷蔵庫に残ったお刺身を見て「まだいけそう?」と迷ったこと、きっと一度や二度ではないはず。
でも、見た目や臭いのちょっとした変化が、食中毒につながることもあるんです。
このセクションでは「お刺身が傷んでいるかどうか」を見分ける具体的なポイントを、見た目・臭い・感触の3方向からわかりやすく紹介していきますね。
見た目の変化(色、ドリップなど)
まずは見た目です。お刺身はとてもデリケートな食品なので、傷み始めるとすぐに見た目に変化が出てきます。
・表面にテカリではなく「曇った感じ」がある
・パックの底にドリップ(血や水分)がたくさん出ている
これらは劣化のサイン。
特にドリップが多いお刺身は雑菌が繁殖している可能性が高く、要注意です。
臭いで判断する方法
新鮮なお刺身は、海の香りや素材本来の匂いがする程度で、決してツンとするような異臭はありません。
傷んだお刺身には以下のような異変があります。
・生臭さが強くなっている
・魚の腐ったようなにおいがする
匂いは特にわかりやすいサインです。「あれ?」と思ったら、口に入れる前にストップしましょう!
触ったときの感触(ぬめりなど)
指でそっと触れたときの感触も重要です。
・手にべたつくような違和感が残る
・身がふにゃっと柔らかく、弾力がなくなっている
新鮮なお刺身は、プリッとした弾力があるもの。
それがなくなっている場合は、かなり劣化が進んでいると考えたほうがよいでしょう。
ひとつでも異常があれば食べないこと
ここまでに紹介した「見た目」「臭い」「感触」のうち、ひとつでも異常があれば、食べない判断がベストです。
「もったいないから」という気持ち、すごくよくわかります。けれど、お腹を壊してしまったら、それこそ一日が台無しです。
少しでも「おかしいかも」と思ったら、その直感を信じてください。迷ったときは、“やめておく”のが安全への近道です。
翌日でも食べるなら、アレンジしてリスクを減らそう
「見た目も臭いも大丈夫そうだし、まだ食べられるかも…?」
そう感じたとしても、お刺身はやっぱり生もの。安全性を考えると、そのまま食べるのは避けた方が安心です。
そこでおすすめなのが、加熱したり、味付けを工夫してアレンジする方法です。
ちょっとしたひと手間で、ぐっとリスクを減らせますし、なにより美味しくリメイクできるんです。
このセクションでは、翌日でもおいしく、安全に楽しめるアレンジ方法をご紹介していきます!
加熱して食べる(焼き物・汁物など)
生では不安でも、加熱すれば雑菌や寄生虫のリスクをぐっと抑えることができます。味も変わって、新しい楽しみ方になるかもしれません。
刺身の照り焼きや炒め物に

たとえば、マグロやカツオなどの赤身系なら、軽く炒めて照り焼き風にするのがおすすめ。
醤油・みりん・酒でサッと味付けするだけで、白いご飯にぴったりのおかずに早変わりです。
白身魚やイカも、野菜と一緒に炒めて中華風にしてもおいしいですよ。
みそ汁や鍋の具として使う

ダシを効かせたお味噌汁に、ぶつ切りにした刺身を入れるだけでも立派な一品。
特にサーモンや鯛などは、味がしっかり出て風味も豊かに。あら汁風になります。
冬場なら、寄せ鍋や石狩鍋風にアレンジして、余り野菜と一緒に煮込むのもおすすめです。
味付けで菌の増殖を抑える(漬け・ユッケ風など)
加熱以外では、「調味料の力」を借りて安全性を高める方法もあります。
殺菌効果や浸透圧で菌の増殖を抑える効果が期待できるんです。
しょうゆやみそを使った「漬け」で安心度アップ

いちばん定番なのが醤油漬け。
マグロやカツオを中心に、醤油・みりん・酒を混ぜたタレに30分〜1時間ほど漬けておくだけ。
卵黄や白ごまをのせて「漬け丼」にすると、翌日でもしっかり楽しめます。
味噌ベースで漬ける「西京漬け風」もアリです。
レモンや酢を使ったマリネや南蛮漬け風もおすすめ

刺身をスライスして、玉ねぎやパプリカなどの野菜と一緒に酢漬けにすれば、マリネ風のさっぱりおかずに。
お酢やレモンには殺菌作用があるため、ただ漬けるよりも安心度が増します。
また、刺身を揚げてから甘酢に漬ければ、南蛮漬け風にも。これなら白身魚も大活躍です。
このように、もうダメかなと思ったお刺身でも、アレンジ次第で安心しておいしく食べる方法はたくさんあります。
ただし、見た目や臭いに違和感がある場合は、無理せず処分するのが一番。
「もったいない」気持ちも大事ですが、「体にやさしい選択」を心がけてくださいね。
お刺身を翌日に持ち越すなら?正しい保存方法
「ちょっと食べきれなかったから、明日食べようかな〜」なんて時、保存の仕方ひとつで安全性や美味しさが大きく変わります。
ここでは、冷蔵・冷凍それぞれの保存方法とポイントをご紹介します!
種類によっても違いがあるので、注意点も一緒にチェックしてみてくださいね。
冷蔵保存のポイント
お刺身を翌日も美味しく安全に食べるためには、まず冷蔵保存の基本を押さえておきたいところ。
特に、スーパーで買ってきたパックのまま放置…なんてのはNG!
以下のポイントを押さえることで、菌の繁殖を防ぎつつ、劣化を遅らせることができます。
買ってきたらすぐに密閉&チルド室へ
お刺身は温度変化に弱い食品。家に帰ったらすぐ、密閉容器やラップで包んでチルド室(0~1℃)に保存しましょう。
スーパーのパックのままでは空気に触れやすく、乾燥や雑菌の心配があるので注意が必要です。
また、トレーの底にドリップが溜まっている場合は、キッチンペーパーでしっかり水分を吸い取ってから保存するのもポイントですよ。
刺身の種類による違い(白身、赤身、貝類など)
刺身の種類によっても、傷みやすさや保存方法の適性が変わります。
ざっくり言うと、赤身(マグロ・カツオなど)は比較的日持ちしやすく、白身魚(鯛・ヒラメなど)はデリケートで風味が落ちやすいタイプ。
さらに、青魚(アジ・イワシ・サンマなど)は脂が多く酸化しやすいため、特に注意が必要です!
貝類やタコなどは冷えすぎると食感が変わることもあるので、温度管理に気をつけながら早めに使い切るのがベターです。
冷凍保存はできる?
お刺身は「生もの」なので冷凍に不向きな印象がありますが、種類と処理の仕方によっては冷凍保存も可能です!
ただし、風味や食感が多少変わることを前提に、うまく活用するのがポイントですよ。
冷凍に向かない刺身もある
すべてのお刺身が冷凍OKというわけではありません。
例えば、イカや貝類などは解凍後に食感が変わりやすく、あまりおすすめできません。
また、脂の多い青魚(アジ・イワシ・サンマなど)も酸化が進みやすいため、冷凍には不向きです。
保存する場合は早めに使い切ることが前提になります。
一方、マグロやサーモン、白身魚などは比較的冷凍に強い部類。しっかりと下処理をしてから冷凍しましょう。
冷凍する場合の下処理と保存期間
冷凍するなら、下処理と保存方法をしっかりすることで、味や食感の劣化を最小限にできます。

- 水分をしっかり拭き取る(キッチンペーパーなどで)
- 1食分ずつラップで包む → フリーザーバッグに入れる
- できれば金属トレイで急速冷凍するのがおすすめ
- 保存期間は 1週間以内(青魚は3~4日が目安)
保存期間は約1週間が目安ですが、風味を損なわないためにも3〜5日以内に食べきるのが理想的です。
ちなみに、解凍は冷蔵庫内でゆっくり行うのがベスト。常温解凍は菌が繁殖しやすいので避けましょう。
※ 解凍後は必ず加熱調理に使うようにしましょう!(照り焼きや味噌汁などがおすすめ)
・種類によって保存に向いてるか違うので要チェック!
・冷凍はできるけど、青魚や弾力系は慎重に
・安全に食べるには「できるだけ早く消費するのが一番」
よくある疑問に答えます(FAQ)
お刺身って「ナマモノ」だからこそ、いろいろと気になる疑問が出てくるものです。
ここでは、よく聞かれる5つの質問について、やさしく丁寧にお答えしていきます!
消費期限を1日過ぎただけなら問題ないの?
結論からいうと、「自己判断にまかせられるけど、けっこう危険」です。
たとえば冷蔵庫でしっかり保存していた場合でも、見た目や匂い、ヌメリなどの変化が出ていたら絶対に食べないでください。
お刺身はもともと「当日中に食べるのが前提」で作られているため、1日過ぎただけでも菌が増殖している可能性があります。
とくに青魚(アジやサバ、サンマなど)は傷みが早く、ヒスタミン中毒のリスクも。
どうしても食べるなら、見た目・匂い・食感をしっかりチェックし、できれば加熱や漬けにするなどしてリスクを下げましょう。
刺身を加熱すれば安全になる?
ある程度は「YES」です! でも、加熱してもすべてのリスクをゼロにはできません。
たとえばサルモネラ菌やリステリア菌など、多くの食中毒菌は加熱で死滅します。
なので、刺身を照り焼きやみそ汁の具にするなどの調理法は、かなり効果的な対策になります。
ただし、すでに毒素が発生していた場合や、腐敗が進んでいた場合には加熱してもダメ。
「変なにおいがする」「色がくすんでいる」「ネバネバしている」などの異常がある刺身は、加熱して食べるより廃棄を!
冷凍刺身のお刺身も、解凍後はすぐ食べるべき?
はい、解凍したらその日のうちに食べきるのが鉄則!
一度解凍した刺身は、冷蔵庫に入れておいても傷むスピードがとても早いんです。
とくに「自然解凍」や「常温で放置してしまった」場合は、雑菌がどんどん繁殖してしまう可能性も。
さらに、「再冷凍」はNG。食感も味も落ちますし、安全性も低くなります。
解凍した刺身は、その日のうちに!これが美味しく食べるための合言葉です。
わさびや醤油って、殺菌効果があるの?
たしかに、わさびや醤油には軽い抗菌作用があります。
でもこれは、あくまでも「補助的な役割」と考えてください。
たとえば食中毒菌を完全に殺すほどの力はありませんし、傷んだ刺身を安全にしてくれるわけでもないんです。
なので「わさびがあるから大丈夫!」なんて油断せずに、刺身そのものの鮮度を一番にチェックすることが大切です!
パックのお刺身、ラップを開けずに保存すれば長持ちする?
これもよくある誤解のひとつです!
実は、市販のパック刺身のラップやフタは、「長期保存用」ではなく、販売用に見栄えを保つための簡易包装。
パックのままだと、中に水分がこもったり、空気が入り込んで菌が繁殖しやすくなることもあります。
買ってきたら、すぐに清潔な保存容器に移してラップ密閉し、チルド室や冷蔵庫の奥の方で保存するのが正解です。
まとめ
ここまで、お刺身の「翌日以降は食べられるの?」「どう保存すればいいの?」という疑問について、いろいろな視点からお話してきました。
最後に、大事なポイントをぎゅっとまとめておきましょう!
消費期限を守ることが一番大切
お刺身はデリケートなナマモノ。やはり「消費期限内に食べ切る」のがベストです。
とくに夏場や室温が高い時期は、ちょっとした時間差でも傷んでしまう可能性があります。
消費期限を過ぎた刺身は、自己判断での飲食は避けたほうが安全です。お腹を壊してしまったら、せっかくの美味しさも台無しですからね。
どうしても食べたい場合は「見極め+加熱やアレンジ」で対策を
とはいえ、「うっかり食べ忘れた」「もったいなくて捨てられない」という気持ちもわかります!
そんなときは、まず色・におい・ぬめりなどをしっかりチェック。
そして、加熱調理(照り焼き、炒め物、味噌汁など)やアレンジレシピで、安全に食べる工夫をしましょう。
また、どうしても不安なときは、無理せず思い切って処分するのも「正しい選択」です。
体の健康にはかえられませんからね。
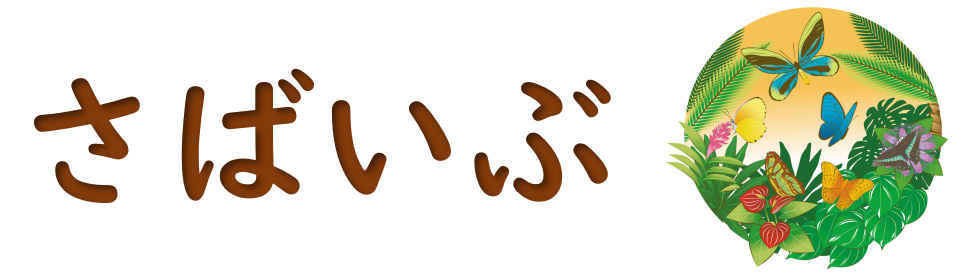


コメント