今年は喪中で…「お正月におせちって食べても大丈夫かな?」ってモヤモヤしますよね。
結論を先に言うと、喪中でもおせちを食べること自体はNGではありません。
ただし、忌中(四十九日)以内は控えるのが一般的で、華やかなお祝いムードを避けて、ちょっと落ち着いた雰囲気にするのが安心です。
最近は、家族の気持ちや状況を大切にして、静かなお正月を過ごすご家庭も増えていますよ。
喪中のお正月におせちはどうする?
「今年は喪中だし…おせちってどうしたらいいんだろ?」って、ちょっと迷っちゃいますよね。
気持ちが落ち着かない時期でもありますし、無理に“いつも通り”をしなくても大丈夫です。
まず結論からお伝えすると、
ただし、故人を偲ぶ期間の気持ちや、ご家族の心の状態を大切にするのが一番。
「無理なく、心穏やかに過ごせる方法」を選べばOKです。
喪中でもおせちは“絶対ダメ”ではない理由
おせちはもともと「一年を祝う」「豊作を願う」といった縁起料理。
たしかに“お祝い”という意味合いはありますが、
「食べる = お祝いをする」ということではありません。
実際、喪中だからおせち禁止という明確なルールはありませんし、「普段通りの食事としていただく」という方も増えています。
自分や家族の気持ちが「無理なく過ごせる形」であれば、控えめなおせちを楽しんでも大丈夫なんです。
ただし忌中(四十九日以内)は控えるのが一般的
一方で、忌中(四十九日)までは“祝い事を控える”期間とされています。
この時期に華やかな祝い料理を囲むのは、ちょっと気持ちが落ち着かない…という方がほとんど。
なので、
というのが実情です。
宗派によって考え方が異なることも
喪中・忌中の考え方は、仏教や神道、地域の風習によっても違いがあります。
「四十九日より長く慎む」「特に決まりなく家族の意思で」など、家庭ごとにスタイルがあるので、
でOKです。
家族の気持ちと故人への配慮が一番大切
そしてなにより大切なのは、気持ちの部分。
- 今年は静かに過ごしたい
- 少しだけお正月気分を感じたい
- いつも通りで心が落ち着く
どれも間違いじゃありません。
それが一番の“正解”です。
喪中におせちを食べる場合の注意点
喪中でもおせちを食べることはできますが、やっぱり「祝いの演出を控える」ことが大切です。
ポイントは、「お祝い料理」から「落ち着いたお正月ごはん」にトーンを変えること。
見た目や意味を少しだけアレンジするだけで、ぐっと気持ちに寄り添ったおせちになりますよ。
祝い料理は控えめに(鯛・紅白・海老など)

おせちにはそれぞれ縁起の意味が込められています。
たとえば「鯛=めでたい」「海老=長寿」「紅白=お祝いの色」など、まさに“祝い料理”の代表格。
喪中の間は、こうした強い祝いの象徴になる食材は控えめにするのがおすすめです。
代わりに、煮物・田作り・黒豆といった「日常でも食べられるおせち」を中心にすれば、落ち着いた雰囲気のまま、しっかりお正月気分を味わえます。
重箱は使わず普段の器に盛り付ける

おせちといえば重箱ですが、重ねる=「めでたさを重ねる」意味を持ちます。
そのため喪中の間は、重箱を使わず、普段の器に盛り付けるのが無難です。
白い皿や木のお皿など、素朴で温かみのある器を使うと、落ち着いた雰囲気に仕上がって気持ちも穏やかになります。
器を選ぶだけで“静かな華やかさ”を演出できますよ。
祝箸や金粉など「お祝い演出」は避ける

喪中のお正月では、箸や飾り付けにも気を配るとより丁寧です。
祝い箸(両端が細い柳の箸)は「神様と人が一緒に食事をする」という意味があり、お祝い事に使うものなので、喪中の席では避けましょう。
代わりに、普段使いの箸や木製のシンプルなものを使えばOKです。
また、おせちに金粉を散らしたり、水引や紅白の飾りをつけるなどの「お祝い演出」も控えるのが基本。
静かなお正月らしい、しっとりとした雰囲気になります。
「控える」場合の代替案|ふせちや普段の料理でも◎
「喪中だからおせちはやめよう」と思っても、まったく何も食べずにお正月を過ごすのは、ちょっと寂しいもの。
最近は、お祝い感を抑えながらも“新しい年を迎える食事”を楽しむために、「ふせち」やシンプルな家庭料理を取り入れるご家庭が増えています。
ふだんの料理+少しだけ縁起を担がない“ふせち”

「ふせち」とは、“おせちを控える”という意味から生まれた、比較的新しい言葉です。
明確な決まりごとはなく、「お祝いの料理はちょっと…でも新年の雰囲気は味わいたい」という気持ちから、各家庭で自然に工夫されるようになりました。
最近では、デパートや通販でも「ふせちセット」として控えめなおせちが販売されているほど。
つまり、無理に伝統に合わせなくても、“静かに新しい年を迎える料理”として自由に楽しんでいいんです。
たとえば、
- 煮物、だし巻き卵、里芋の煮っころがし
- 焼き魚やお吸い物など、いつもの食卓に近い献立
など、あたたかくて落ち着いた料理で十分。
「喪中だからこそ、家族で静かに食卓を囲む時間がありがたい」、そんな気持ちを大切にすれば、それも立派なお正月の迎え方です。
精進おせち・あたたかい煮物やお雑煮という選択
もうひとつの方法が、精進料理風のおせちです。
肉や魚を使わず、野菜・豆・海藻などを中心に作る「精進おせち」は、故人を偲びながら穏やかに過ごしたいご家庭にぴったり。
また、「あたたかい煮物」や「お雑煮」だけで新年を迎えるのも、とても自然で落ち着いた選択です。
特にお雑煮は地域によって味も具材も違うので、「うちの味」でゆっくり味わうのも素敵な過ごし方ですね。
「食でしっぽりゆっくり」なお正月の例

たとえば、こんなメニューはいかがでしょう?
- 根菜たっぷりの筑前煮
- 白味噌仕立てのお雑煮
- お豆腐とわかめのお吸い物
- 黒豆(まめに暮らす)
派手さはなくても、心がほっとする食卓になります。
それも立派な新年の迎え方ですよ。
そもそも喪中と忌中の違いって?
「喪中」と「忌中」って似ているようで、実は意味が違うんです。
年賀状やおせちなどのマナーを考える上でも、この違いを知っておくと安心ですよ。
喪中=1年程度、忌中=四十九日(目安)
まず、「忌中(きちゅう)」は亡くなってから四十九日までの期間を指します。
この間は“穢(けが)れを避ける期間”とされ、慶事(けいじ)、つまりお祝いごとは控えるのが一般的です。
一方で「喪中(もちゅう)」は、故人を偲びながら静かに過ごす期間を意味し、おおむね1年ほどが目安とされています。
この時期は、必ずしもお祝いを完全に避ける必要はありませんが、派手な宴席などは控えめにするのが無難です。
宗派・地域で違いもあるから柔軟に
ただし、喪中・忌中の期間は宗派や地域によって差があります。
たとえば浄土真宗では、「死は忌むものではない」との教えから、忌中の考え方そのものがない場合もあります。
つまり、「うちはどうなの?」と思ったときは、菩提寺や家族年長者に相談しておくと安心です。
形式よりも、「みんなが気持ちよく新年を迎えられるか」を大切にするのが一番ですね。
よくある疑問
喪中のお正月は、どう過ごすのが正解か悩むもの。
ここでは、実際によくある質問をピックアップして、わかりやすくお答えします。
既におせちを予約しちゃった…どうする?
「喪中だと知らずに予約していた」という方、実はけっこう多いんです。
結論から言うと、無理にキャンセルする必要はありません。
もし忌中(四十九日以内)でなければ、届いたおせちは「お祝い感を控えめにアレンジしていただく」のが現実的です。
たとえば、
紅白かまぼこ・鯛・海老などの“お祝い食材”は避け、黒豆や煮しめ、昆布巻き、田作りなど、落ち着いた味わいの料理を中心に盛り付けるとよいでしょう。
また、重箱から普段使いのお皿に盛り付け替えるだけでも雰囲気が和らぎます。
「華やかな席」ではなく、「家族で静かにいただく食卓」へと自然に切り替えられますよ。
年末に届くおせちを松の内(1月7日ごろ)過ぎまで置いておくのは難しいので、保存に無理のない範囲で、感謝の気持ちを込めていただくのが一番です。
年越しそばやお雑煮はOK?
はい、基本的には大丈夫です。
どちらも「お祝い料理」ではなく、年を越す・新しい年を迎えるための習慣食だからです。
ただし、気持ち的に控えたい場合は、紅白かまぼこやエビなど“祝い食材”を使わず、シンプルに出汁と具材でほっとする味に整えるのも良いですね。
特にお雑煮は地方色が強いので、「お祝い感を抑えた我が家流」を楽しむ形でまったく問題ありません。
親戚が「気にしなくていい」と言うけど…
これは本当によくある悩みですよね。
地域や家庭によって考え方が違うので、意見がぶつかることもあります。
ただ、マナーとしては“どちらか一方を正解としない”のが正解です。
たとえば、親戚が「気にしなくていい」と言うなら、「ありがとうございます。うちは少し控えめにしておきますね」と、柔らかく受け流すのが一番スマート。
喪中の過ごし方は、形式よりも心の持ち方。
お互いの気持ちを尊重して穏やかに過ごせたなら、それが一番の供養にもなります。
まとめ|心を込めて過ごす“静かなお正月”も素敵に
喪中のお正月は、にぎやかなお祝いよりも、家族の気持ちを大切にした穏やかな時間を過ごすのが一番です。
おせち料理を食べること自体はNGではありませんが、忌中であれば控えめに、喪中であっても派手な演出は避けて、「今ある日常を静かに味わう」という気持ちで過ごすといいですね。
重箱や祝い箸を使わず、普段の器に料理を盛るだけでも、気持ちが少し落ち着いて、特別な“静かなお正月”になります。
何より大切なのは、形式よりも「故人を思い、家族を思う気持ち」。
それがあれば、どんな過ごし方でも立派なお正月です。
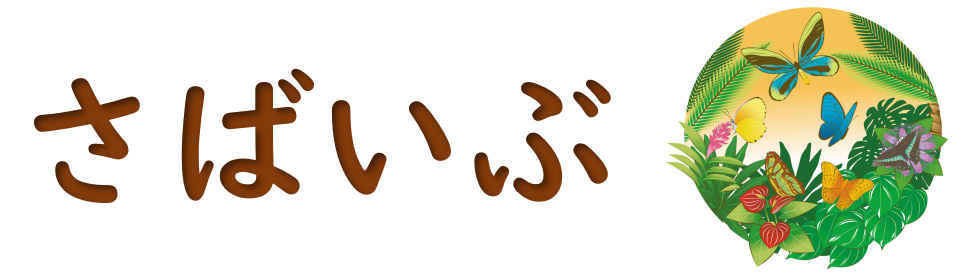


コメント