『うなぎと梅干しの食べ合わせって、本当にダメなの?』
夏のスタミナ食といえば、やっぱりうなぎ。
そこにさっぱり梅干しを添えたら最高じゃん!って思いますよね?
でも昔から『鰻と梅干しの食べ合わせはよくない』なんて言われてきました。
「ほんとにダメなの?」「食べたらお腹壊す?」「何か根拠があるの?」と不安になる人もいるはず。
でもご安心を。実はこれ、迷信に近い言い伝えなんです。
この記事では、
まで、うなぎ好きの筆者が体験談も交えて徹底解説していきます。
鰻と梅干しの食べ合わせは本当に悪いの?
「鰻と梅干しは一緒に食べちゃダメ」と聞いたことがある方、多いですよね。
昔から親や祖父母に言われて「なんとなく避けてきた」なんて人もいるかもしれません。
結論から言うと、鰻と梅干しの食べ合わせが体に悪い、という科学的な根拠はありません。
むしろ、脂がのった鰻とうまく付き合ううえで、梅干しの酸味が消化を助けたり、さっぱり感をプラスしてくれることもあるんです。
じゃあ、どうして「食べ合わせが悪い」なんて言われるようになったのか?
実はその背景には、昔の食文化や保存技術の事情、体調への配慮などが関わっているんですよ。
このあと詳しく、江戸時代の言い伝えから現代栄養学までを順に見ていきますが、まずは安心してください。
「鰻と梅干しを一緒に食べたからお腹を壊す」といった心配はないんです。
鰻と梅干しの食べ合わせの言い伝えとは?
「鰻と梅干しは一緒に食べるな」という言い伝え、実はかなり古い時代から伝わっているものなんです。
迷信のようでいて、当時の暮らしや食文化を反映している部分もあるんですよ。
江戸時代からの「食べ合わせ」の考え方
江戸時代の人々は、今のように栄養学の知識があったわけではありません。
その代わりに「この食べ物とこの食べ物を一緒にすると体に良くないらしい」という“経験則”が重視されていました。
これを「食い合わせ」や「食べ合わせ」と呼んでいたんですね。
例えば、
- 天ぷらとスイカ
- 蟹と柿
など、いくつもの「悪い組み合わせ」が言い伝えとして残っています。
これは「体を冷やす」「消化に悪い」などの理由づけが多く、現代の科学的根拠とはちょっと違います。
むしろ「食べ過ぎないように注意するための知恵」だったとも考えられています。

なぜ「鰻と梅干しはダメ」と言われたのか
さて、鰻と梅干しがNGとされた理由には、いくつかの説があります。
まず、鰻は脂がのっていて高カロリー。梅干しは酸味が強い食べ物です。この二つを一緒に食べると「消化不良を起こすのではないか」と考えられていました。
もうひとつは、当時の保存環境。冷蔵庫のない時代に夏場の鰻を食べるのはリスクが高かったんです。そこで「梅干しと一緒に食べると危ない」と戒めることで、食べ方や量を抑える狙いもあったと言われています。
つまりこの言い伝えは、単純に「食べると体に悪い」というより、「ぜいたく品の鰻を食べすぎないように」「体調を崩さないように」という昔の人の生活の知恵だったわけです。
うなぎと梅干しを一緒に食べると体に悪いの?

昔から「うなぎと梅干しは一緒に食べちゃダメ」と言われてきましたが、実際のところ本当に体に悪いのでしょうか?
現代の視点から見ていくと、答えは意外にシンプルなんです。
消化の観点から見る「うなぎ+梅干し」
うなぎは脂がのっていて、とても消化に時間がかかる食材です。
一方で梅干しの酸味に含まれるクエン酸は、胃酸の分泌をサポートしてくれる働きがあります。
つまり、実際には「うなぎの消化を助ける」方向に働く可能性があるんです。
「脂っこいうなぎを食べたあとに、梅干しでさっぱりしたくなる」という感覚は、理にかなっているとも言えますね。
栄養学的に問題はある?
栄養学の観点から見ても、うなぎと梅干しを一緒に食べることに大きなデメリットはありません。
-
うなぎにはビタミンA・ビタミンE・DHA・EPAなど、疲労回復や健康維持に欠かせない栄養素が豊富。
-
梅干しにはクエン酸やポリフェノールが含まれ、疲労回復や抗酸化作用に役立つ。
この二つを組み合わせると「スタミナ+疲労回復」という、むしろ良い相乗効果が期待できるんです。
ただし注意点がひとつ。
うなぎ自体が高カロリーで消化に負担がかかるので、「食べ過ぎ」にはやっぱり気をつけたいところです。
現代医学から見た食べ合わせの真実
医学的に言えば、「食べ合わせが悪いから健康被害が出る」という証拠はありません。
厚生労働省や栄養学の専門機関でも、うなぎと梅干しを避けるような注意喚起はしていないんです。
むしろ現代医学の立場からすると、この言い伝えは「食べすぎないようにするための戒め」「食中毒リスクを避けるための知恵」という歴史的な側面が強いと考えられます。
だから安心してOK。
体に悪いどころか、バランスよく楽しめばむしろ健康的な組み合わせなんですよ。
鰻と梅干しを一緒に食べるとこんな効果が!
鰻と梅干しは「体に悪い」と言われてきた一方で、実は味覚や食文化、そして季節の食生活の中でメリットの多い組み合わせでもあるんです。
ここからは、実際にどんな効果や魅力があるのかを、味・文化・ライフスタイルの3つの視点から見ていきましょう。
梅干しが鰻をさっぱり美味しくする味覚の相性

脂ののった鰻はごちそう感たっぷりですが、「ちょっと重たい」と感じる人もいますよね。
そんなときに梅干しを合わせると、酸味が口の中をリセットしてくれるので、鰻の旨みを最後まで飽きずに楽しめるんです。
特に蒲焼のような甘辛いタレと梅干しの酸味は相性抜群。
「こってり+さっぱり」という味のコントラストが生まれ、さらに食欲を引き立ててくれます。
江戸の知恵?料理の工夫として残る組み合わせ
面白いのは「鰻と梅干しは食べ合わせが悪い」と言われつつも、実際の料理文化では昔から組み合わせとして活用されてきたことです。
江戸時代から、鰻をさっぱり楽しむ工夫として梅や酢の物を添える習慣があり、現代でも料理店で見かけることがあります。
「体に悪い」と避けられる一方で、「美味しく食べる工夫」としては取り入れられてきた。これは食文化の奥深さを感じさせる点ですね。
実際に楽しめる鰻×梅干し料理の例

・梅肉を添えたうな丼:濃厚なタレの甘さを梅の酸味が引き締めてくれる
・梅干し入りのう巻き:卵の優しい味わいの中で梅がアクセントに
・鰻茶漬けに梅干しをプラス:さっぱりとした後味で、〆の一杯にぴったり
こうした料理は「美味しく仕上げるための知恵」として、実際に食文化の中に根付いているんです。

実際に鰻茶漬けに梅干しを入れて食べてみたんですが…これが驚くほどサッパリ!
〆なのに“もう一杯いけるかも”って思うくらい軽やかでした。『鰻=重たい』というイメージがガラッと変わりますよ。
夏にぴったり!スタミナ食+疲労回復の黄金コンビ
鰻といえば夏の土用の丑の日でもおなじみのスタミナ食。
そこに梅干しを合わせれば、クエン酸による疲労回復作用がプラスされて、夏バテ対策としてさらに効果的になります。
「鰻でしっかり栄養を補給し、梅干しで消化や食欲をサポート」。これぞ夏の理想的な食べ合わせ。
暑さで体力が落ちやすい時期に、まさにうってつけの黄金コンビといえるでしょう。
こうして見てみると、「鰻と梅干し」は単なる迷信を超えて、味覚・食文化・ライフスタイルのすべてでプラス効果をもたらす組み合わせなんです。
うなぎと梅干しの食べ合わせに関するQ&A
うなぎと梅干しの食べ合わせについては、今でも「本当に大丈夫なの?」と気になる人が多いようです。
ここでは、よくある質問をまとめてお答えします。
一緒に食べても本当に大丈夫?
結論から言えば、問題ありません。
栄養学的にも医学的にも「体に悪い」という根拠はなく、むしろ消化を助けたり疲労回復に役立つ可能性があります。安心して召し上がってください。
どんな食べ方ならおすすめ?
おすすめは「うな丼に梅干しを添える」「鰻茶漬けに梅干しを加える」など。
脂っこさをリセットできて、最後まで美味しく食べられます。食欲が落ちやすい夏にもピッタリ。
子どもや高齢者でも問題ない?
基本的には問題ありません。
ただし、うなぎは脂が多く消化に時間がかかるため、胃腸が弱い人は少量から試すのがおすすめです。
梅干しの酸味が強すぎると感じる場合は、はちみつ漬けの梅干しなどを選ぶと食べやすいですよ。
まとめ|鰻と梅干しの食べ合わせは「悪い」どころか相性◎
「うなぎと梅干しは一緒に食べてはいけない」という昔ながらの言い伝え。
実際には医学的な根拠はなく、むしろ「さっぱりと食べやすくする」「スタミナ+疲労回復の相乗効果」といったメリットがあることがわかりました。
もちろん、うなぎは脂が多めでカロリーも高いので「食べ過ぎ注意」という点だけは忘れずに。
バランスよく楽しめば、体に悪いどころか、夏の暑い日や疲れがたまったときにぴったりの組み合わせになります。
昔の知恵としての「食べ合わせの言い伝え」を理解しつつ、現代の食文化では「鰻×梅干し」を賢く楽しむのが一番ですね。
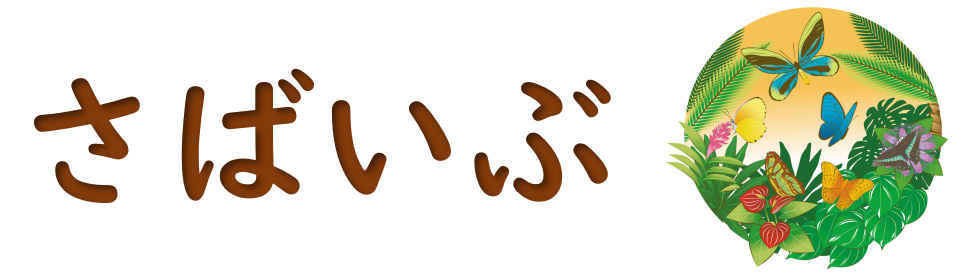



コメント